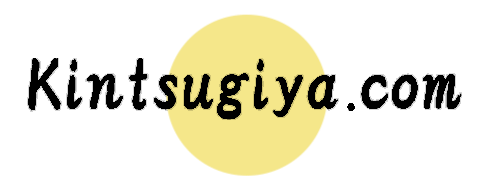金継ぎ(きんつぎ)は陶磁器などが割れたり、欠けたりした部分を修繕する日本伝統の技法です。
金継ぎは、漆などを用いて、多くの工程を数週間かけておこないます。漆による接着の強度は長い歴史が証明しており、あらゆる接着剤の中でも非常に優秀であるとされています。きちんと直したものは、再び、数十年間から数百年間も使うことができるようになります。
技法名のとおり、装飾として金粉が使われることが多くありますが、必ずしも金粉を用いるとは限らず、銀粉を使ったり、黒呂色漆や弁柄漆を使ったものなども、金継ぎの一種です。
作業工程は、対象物の壊れ方や直し方によって異なりますが、おおむね10工程ほどかかります。各工程の間に、漆が硬化する(乾くとも言います)ための期間が3~7日間ほど必要になるため、完成させるまでに長い期間を要します。
金継ぎは、とても多くの技法があります。少し極端な言い方をすれば、「漆を使って接着して、金属粉や色漆などを使って装飾すれば金継ぎ」なので、直し方やデザインはとても自由です。伝統的な技法を用いながら、現代風にも自由に直せることが魅力のひとつであると言えます。
例 割れたお皿を金継ぎする場合の工程
- 直した後の使い方を想定して、直し方とデザインを決める
- 割れた部分をヤスリで削って整える(デザインによっては割れた個所以外も削る)
- 破片同士を漆を使って接着する
- 接着した割れ目の凹凸を漆で埋める
- 埋めた部分を研ぐ(磨く)
- 研いだ部分に漆を下塗りする
- 下塗りした部分を研ぐ(磨く)
- 研いだ部分に漆を上塗りする
- 上塗りした部分を研ぐ(磨く)(必要に応じて8.と9.を数回繰り返す)
- 装飾する(漆で、金粉や銀粉などを接着したり、色漆などを塗る)
- 必要に応じて、金粉や銀粉に漆を薄く塗って装飾を保護する
漆の世界
日本人はおよそ9,000年も前から漆を使用し、食器や工芸品、建築物などの塗料や接着剤として利用してきました。ウルシの栽培、漆の採取や精製の技術は連綿と伝承されてきましたが、現在、漆の国内産地は1道1府11県で生産量は1.8トン、国内自給率は約7%となっています(2022年)。文化庁の方針で2014年度から、国宝・重要文化財建造物の保存修理には原則として国産漆を使用することになりました。しかし、保存修理には年平均約2.2トンの漆が必要といわれ、国産漆の生産拡大が望まれています。
漆は、樹液の分泌が活発になる6月からウルシの木にキズをつけて、そこからにじみ出た樹液を採取します。樹液を採取するのは樹齢10~20年に達した木で、採取したら枯れてしまうので、その年に伐採します。そして、切り株から出た芽を育てて、また同じ営みを繰り返していきます。1本のウルシの木から採れる樹液は約200gで、大変貴重なものです。採取時期によってウルシの特性が異なり、大きく以下の4つに分かれています。
初辺(はつへん) 6月下旬~7月下旬
盛辺(さかりへん) 7月下旬~9月上旬
末辺(すえへん) 9月中旬~10月中旬
裏目(うらめ) 10月下旬~11月上旬
(農林水産省のホームページから抜粋して加筆)